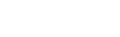ドワンゴにおける
マネジメントとは

TALK MEMBER
-
-
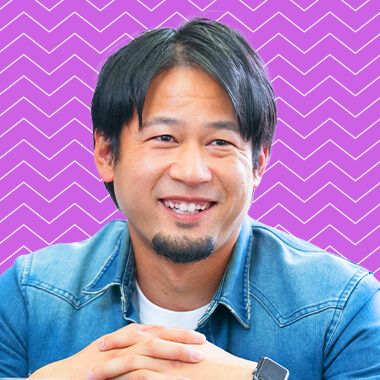
-
浅野 勇貴
営業本部
イベント営業部
2014年8月入社(中途)
営業職
-
-
-
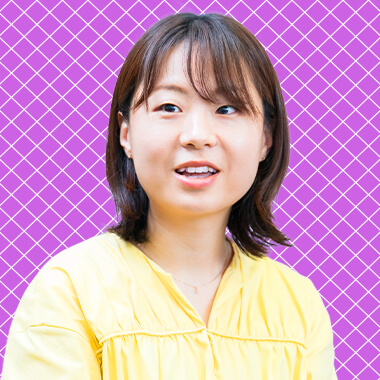
-
國井 理恵子
教育事業本部
コンテンツ開発部
2016年11月入社(中途)
企画職
-
-
-

-
山﨑 康平
ニコニコ事業本部
デザインコミュニケーション室
2006年8月入社(中途)
デザイナー職
-
-
-

-
滝本 なつき
ニコニコ事業本部 チャンネル事業部
(出向:株式会社KADOKAWA)
2016年6月入社(中途)
企画職
-
01現在の仕事内容を教えてください。
-
-

-
ニコニコ生放送やイベントなどのプロデュースや制作を通して、大手ゲームメーカーのプロモーション活動をサポートしています。
-
-
-

-
主な仕事は、学習アプリ「ZEN Study」の教科学習コンテンツの企画制作です。そのほか、角川ドワンゴ学園の生徒や一般会員向けの教材の企画制作、新しい授業の企画なども担当しています。
※「N予備校」は2024年8月末に「ZEN Study」にリニューアルしました
-
-
-

-
この春からは、サービスのUIデザインを主に担当。それまでは、イベントプロモーション用のWeb制作や、ロゴデザインなどのグラフィック制作に携わっていました。
-
-
-

-
主に、ニコニコチャンネルを運営されているオーナーのサポートや、会員数を増やすための施策提案を担当しています。
-
02どんなところに、やりがいを感じますか?
-
-

-
世界的な人気を誇るゲームタイトルのプロモーションに携われるところ。リアルイベントでユーザーが喜んでくれる姿を直接見られることも、やりがいです。
-
-
-

-
「学ぶっておもしろい」と思ってもらえるようなコンテンツを企画することで、生徒の学びをサポートできるのがやりがい。「教育の変革」に取り組めるのも、この仕事の醍醐味です。
-
-
-

-
自分がデザインを担当したサービスがリリースされ、ユーザーからいい反響をいただけたときには最高の気分になります。
-
-
-

-
さまざまなジャンルのニコニコチャンネルを総合的にサポートしているので、作家さんから文化人、声優さん、Vチューバーまで、いろいろな方々と触れ合い、多くの学びや刺激を得られるのが魅力です。
-
03マネージャーとして、
印象に残っているエピソードは?
-
-

-
実力以上の仕事や役割を任せたところ、想像以上に活躍してくれたメンバーがいました。メンバーたちが、期待を超えるパフォーマンスを発揮してくれるとうれしくなります。
-
-
-

-
セクションや部署をまたいで、周囲を巻き込んでいけたこと。そうすることで、より企画のクオリティを高めることができました。マネージャーだからこそ、垣根を越えた声がけがしやすくなったと感じています。
-
-
-

-
あるメンバーに、苦手分野の仕事を任せたことがあったんです。懸命に向き合って見事やり遂げ、「苦手意識がなくなりました」と言われたときは、任せてよかったと誇らしく思いました。
-
-
-

-
ニコニコチャンネルのさらなる会員獲得に向けたキャンペーンを実施する際に、共通のフォーマットや仕組みをつくれたこと。チャンネルオーナーやメンバーの負担軽減に、大きく貢献できました。
-
04仕事をするうえで、大切にしていることは?
-
-

-
クライアントとユーザーのニーズを掛け算したうえで、「新しい価値」「貴重な体験」になりうるかを重視しています。それこそが、私たちの存在意義。この想いは、メンバーたちと共有するよう心掛けています。
-
-
-

-
失敗を恐れることなく、新しいことに挑戦すること。そうしなければ、常識を覆し、ユーザーの期待を超えるサービスを生み出すことはできません。メンバーたちには常々、「失敗してもいい。責任は私がとる」と伝えています。
-
-
-

-
自分の意見に固執しないこと。そのためにも、メンバーとのコミュニケーションにウエイトを置き、日々業務を進めるようにしています。
-
-
-

-
心掛けているのは、メンバーが気持ちよく仕事できる環境づくり。そのために各所と調整や交渉を行ったり、仕組みをつくったりするのが、マネジメントを担う私の仕事だと考えています。
-
05仕事で大変なことや、ツライこととは?
-
-

-
自分が考えた企画が、クライアントに刺さらないときはツライ…。ただ、壁を乗り越えた先に成長があると信じて、苦しみながらも楽しんでいます。
-
-
-

-
前例がないことに、挑戦し続けなければいけないこと。自分なりに正解を考えて、自ら決断して進めていくのは大変です。けれども、だからこそ誰も見たことがないものを生み出していけるのだと思います。
-
-
-

-
マネージャーになりたての頃に自分でやる部分とメンバーに任せる部分の線引きの見極めができず苦労しました。今は、メンバーがいかに業務を進めやすい環境をつくるかに重点を置くようにしています。
-
-
-

-
いろんな価値観を持ったメンバーがいるため、一人ひとりのモチベーションを高めることに苦労。いいところはしっかり褒めるなど、試行錯誤しながらマネジメントに携わっています。
-
06ドワンゴの魅力や、好きなところは?
-
-

-
「できること☓やりたいこと」で、自由に新しいことを生み出していけるところです。新人時代に携わった、車の上に将棋の駒を載せて超一流棋士が対戦する企画は、価値観が変わるほど衝撃的でした。
-
-
-

-
変革を全肯定してくれ、スピード感を持って実行に移していけるのが魅力。日本の教育を変えていけるのは、当社のような会社だと思います
-
-
-

-
当社は、個人の裁量が大きいのが特徴。自分がやりたいと思ったことを次々に具現化していけるので、とても刺激的です。
-
-
-

-
自由な社風で、頑張るも頑張らないも自分次第。初めて挑戦することでも手を挙げればチャレンジさせてもらえるため、高いモチベーションで働けます。
-
07今後の目標を教えてください。
-
-

-
ノウハウを蓄積すると同時にアイデアを磨き、より多くのユーザーに楽しんでもらえる企画を具現化していきたいと思っています。
-
-
-

-
究極の目標は、日本の教育システムを変革し、ドワンゴを「世界のEdTechカンパニー」へと成長させること。その実現に向け、一人でも多くの生徒の学びをサポートし、彼らが一歩先へ進めるためのコンテンツを企画していくことが目標です。
-
-
-

-
4月に現在の部署に異動してきたばかりなので、さまざまな価値観を受け入れ、それらを活かせる組織づくりを行っていきたいと考えています。
-
-
-

-
求められるところで、求められる以上の結果を出すこと。周囲の期待を超える成果を生み出せる、マネージャーを目指したいです。
-
Recruitment
採用 情報。